長岡百花繚乱の紀~『うえだ城下町映画祭・親子トーク』⑤
「今のお話しをお聴きになって、千茱萸さんには、毎年この映画祭のために上田に来ていただいていますが、いかがでしょうか。」と聞かれた千茱萸さん。
「映画は、昨年の3・11のこともありますし、映画は生きていく日々の暮らしの中で、本当に必要なものなのかな、ということは、やはり、少し考えたことはありましたね。それでも、私は監督の映画の手伝いをしたり、ずっと映画の中で暮らしてきたので、特にそう思ってしまったのですが、震災後というのは、映画館などは人が集まってきて危険だからということで、一時期人が入らなくなったりとかもあったのですけれども、でも、やはり人の心の中の元気の素と言いますか、明るい明日、映画館の暗闇から一歩外に出たときに、何か新しい明るい希望を灯す力のひとつになれば、映画は本当に喜んでくれているのではないかなと思っていますし、実際に、私は今年で10回目になるのですが、自主制作映画のコンテストは10回目で、映画祭自体は16回目ということで、私も全国色々なところの映画祭に行きますけれども、この続けるということが本当に大変なのですね。やめるのは簡単なのですが。だから、私も、去年、今年と、映画祭をやめちゃうんじゃないかな、と、実は凄くドキドキしていたのですが、特に自主制作映画という、映画のビジネスということではない、お金儲け主義では全くないところで、賞金のことだけではないですけれども、副賞も美味しい上田の信州ハムですとか、美味しいものセットを、映画を創るときはお腹も空きますので、皆さんが映画を創る際に少しでもお腹の足しになればということで、こちらのスタッフの方も考えていただいているのですけれども、何か、そういう拝金主義ではない、映画の心の部分を、この上田の映画祭の方たちは、本当に考えてくださっているのだなということが、今年で10回目ということで、去年からの1年間を振り返っても、本当に、今年62本もの応募作品があったということが、こんなに大変なときに、こんなにたくさんの応募をしてくれたというのが、感動というか感謝の気持ちでいっぱいで、これは、こういうバックグラウンド、心を育てるという上田のバックグラウンドが背景としてあったからじゃないかなと思っています。」
この言葉を受けて「今日は、映画祭のスタッフはもちろんですが、市長もお二人のお言葉を聞いて、映画祭を当分続けないといけないな、という義務感にかられていると思います。」と気を引き締める司会者。
「継続するということが一番大事なのです。やめてしまうと、そこで歴史が止まりますが、それだけではない。過去になってしまうのです。これは、過去にしないで、いつまでも未来を見続けるということが大事で、今日も、私があそこから見ていたら、若い監督さんが表彰を受けていましたが、この人たちが未来の映画を創るのです。未来の映画の歴史を産む人たちなのです。映画の物語に立っているということですね。逆に、今日、この場に立った人たちは、そのことから、「よし、未来の世界の映画は僕がやる」という自覚をもってほしいし、同時に上田の皆さんは、未来につながる人たちを送り出したということです。僕なんかは、ドキドキしながら見ていました。僕はお爺ちゃんだから、頑張ってもあと30年しかないなぁ、と(笑)。新藤監督は、100歳まででしたから、そこまでは目標にしなくてはならない。そうすると、彼らはあと80年は映画を創れるなぁ、と。80年もこれから映画を創ったら、凄いことになりますよ。あなた方自身も、自分でもびっくりするような成長をしますよ。その第一歩が、ここから始まっているということの意味。だから持続しないといけないのですね。」
「本当に、第一回目の自主映画祭のときは、お客様も関係者やゲストの方が多かったのですね。でも、その中に、入江監督がいて、いまは『サイタマノラッパー』という素晴らしい作品を創っているのですが、その入江君が一番最初のときで、ずらっと壇上に並んだときに、お客さんはたぶんスタッフの方が多かったのでしょうけれども、でも、そこから出発して、今は全国区でやっていて、実は、この度、今日これから上映させていただく『この空の花~長岡花火物語』がTAMA映画祭で優秀賞をいただいたのですけれども、そこでも『サイタマノラッパー』は同列で並んでいます。ここで出発した作家さんが、そうやってそこまで大きく、入江君だけに限らず、本当に色々な方がここから飛び出て行っていますので、ぜひぜひ皆さん、若い方は本当に大変なので、応援してあげていただきたいなと思います。」と付け加える千茱萸さん。

「入江君が10年前のここで賞をもらって、この間、日本の映画監督をまとめた本が出ましたが、僕は年寄りだから、前の方のページに乗っていますけれども、入江君も同じ本に載っている。多分、いま読む読者からすれば、入江は良いことを言っているなぁ。大林というお爺ちゃんはあんなことを言っているのか、と、僕の方が脇役になっていますよ。もう、そういう時代なのだから、それがこの10年の歴史です。上田の10年の歴史で、それを作ったということは、凄いことです。今日、僕はこの会場の熱気にびっくりしました。」
と、続けることの大切さを伝えるお二人のお言葉に
「今日は、若い人たちにもたくさん来ていただいているので、ぜひ、いまのお二人のお言葉をエネルギーにして、80年ということですから、ずっと情熱を持ち続けていただきたいですね。」と司会者。
続いて、この日上映された『淀川長治物語・神戸篇 サイナラ』など監督ご自身の作品を引き合いに出して-
「今日観てくださったこの上田で撮影した『淀川長治物語・神戸篇 サイナラ』という映画も、淀川長治さんのことを画いたものですが、これは元々、テレビのドラマとして出発したものなのですね。でも、その予算ではとても創れなかった。それで、うちの恭子さんが、これは自主映画で創ってしまって、創った映画をテレビでオンエアしてもらいましょうよ、と、自主映画ということで、こんな機械1台で編集したのですよ。CGも何も使うお金なんてありませんからね。しかも、合成用のキャメラなんてないから、揺れているのね。でも、これはプロの世界では、揺れているぞ、と言われて使えない。テレビ局だったら、そんなものは使わせてもらえないけれども、淀川さんが現役だったころにあった機材で創ろうということをひとつの思想としている訳で、これは自主映画だからできるのですね。だから、上田にロケに来て、合成がたくさんあるのだけれども、お金がないから、ベニヤ板にグリーンを塗って、それをその辺にまき散らしてね、プロの方だったらこんなものは撮りませんよ、とプロのカメラマンだったら言うだろうというような状況の中で、あれだけのものを創ってしまう。『HOUSE ハウス』がそうでしょう。今日、この後上映する『この空の花~長岡花火物語』というのも、自主映画です。いま話したTAMA映画祭や、嬉しいのは、木下惠介監督が今年で生誕100年ですが、今度、はままつ映画祭で木下さんが戦争中に創られた『陸軍』という映画と『この空の花~長岡花火物語』を2本立てで上映してくださる。あるいは、文科省が日本映画の1本として韓国で上映をしてくださる。この作品が、そのような評価を受けてきている訳ですが、これも自主映画です。もちろん、テレビ局や色々なところも協力してくれていますが、それだけでは成り立ちません。長岡というまちの市民が、老後のためにと蓄えておいたお金までも投じてくれた。だから、長岡市民の自主映画であり、それをうちの恭子さんがプロデュースするという。我々の家族だけでやっている小さな自主映画のプロダクションが手伝って、そして、それを上映する。そうすると、今日も長岡の市長代理の人が、ここに来ちゃっているという。そう言えば、長岡の森民夫市長が、いま全国市長会の会長さんをやられていて、当時の母袋市長が副会長をされていましたね。それに『22才の別れ』では、前市長会会長の大分県臼杵市の後藤市長が出演しているのですね。別に、私はそのようなことを組み合わせてはいませんよ。私が創りたい映画を、創りたいように創ったら、そのまちの市長さんが、あるいは、そういう市長さんを選んだ市民の人たちが、みんな素晴らしい人たちだということを映画が証明してくれるということですね。」
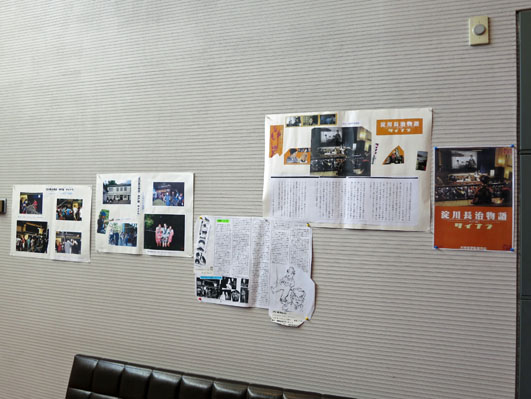
(会場内には、『淀川長治物語・神戸篇 サイナラ』のロケ当時を紹介するコーナーもありました。中には、今や大女優となった宮崎あおいさんがまだ中学生だったころの懐かしい写真も。)
「今日は、大林宣彦監督の映画を『淀川長治物語・神戸篇 サイナラ』、『HOUSE ハウス』、そして最新作の『この空の花~長岡花火物語』ということですから、今日いらっしゃった皆さんは、色々とターニングポイントとなるような映画を全て観られるということで、本当に幸運ですね。」と話す司会者。
「特に、自主映画ということで、私たちは自主映画のベテランですから、いまは企業の映画だから企業の映画を創るという時代でもないですしね。山田洋次さんという方は、いま日本でほとんど一人か二人しか残っていない映画監督ですね。松竹の映画監督ですが、僕らは、そういう意味での映画監督ではないですから。その山田洋次さんが、松竹の正月映画として予定をされていた『東京家族』という映画ですが、あの3・11のときに私は洋次さんから電話をもらいました。「大林さん、3・11前に描いたシナリオでそのまま映画を創ったらダメですよね。僕はこれをやめて、1年休んで、それから創ります。実は、『東京家族』という物語を、3・11以降にもう一度見直したのです。そうしたら、あれは全カットに戦争が映っていました。小津安二郎さんは、戦争の中で映画を創ったり断念してきたりしてきた先輩だから、全部そういう想いが映っているのです。僕らは、そういうことには気付かない。山田さんは、3・11以降にそれに気が付かれて、「大林さん、僕が今度創る『東京家族』には、全カットに放射線が映っていなくてはいけませんね。そのために、僕は1年待ちますよ。」と。松竹の映画監督である山田洋次さんも、そういう自主映画の精神で撮られたから、今度の『東京家族』は、今までの山田洋次作品を超える素晴らしい作品になっているのではないかと思っています。制作が松竹ではないですよね。東京家族製作委員会となっていますよね。黒澤さんだって、東宝を辞めて晩年は自主映画になったでしょう。新藤兼人さんも、松竹を辞めて、自主映画だからこそ、『1枚のハガキ』のような自由奔放な芸術性の高い作品を創られた。そこをいくと、今日デビューされた人たちは、最初から自主映画という商売人ではなく芸術家である訳ですから。さて、芸術とは何か。それは、今日ここに来るときに僕が見た紅葉です。「芸術の秋だね」と僕が言ったとき、恭子さんが、「秋が芸術なのよね」と言いました。雲が綺麗でしたが、雲は気象とか色々なところからできるものだけれども、僕たちから見ると、象の形をしていたり、麒麟の形をしていたり、芸術なのですね。「雲は天才である」と言いましたね。つまり、より人間的であると言うことが芸術なのですね。そのためにも、これからデビューする映画作家には、風のため、名誉のためではなく、人間のため、世界の未来の平和のために、映画を創っていくということを決心するのが、3・11以降の私たちの努めだというように思います。」と大林監督。

(りょう)
つづく
「映画は、昨年の3・11のこともありますし、映画は生きていく日々の暮らしの中で、本当に必要なものなのかな、ということは、やはり、少し考えたことはありましたね。それでも、私は監督の映画の手伝いをしたり、ずっと映画の中で暮らしてきたので、特にそう思ってしまったのですが、震災後というのは、映画館などは人が集まってきて危険だからということで、一時期人が入らなくなったりとかもあったのですけれども、でも、やはり人の心の中の元気の素と言いますか、明るい明日、映画館の暗闇から一歩外に出たときに、何か新しい明るい希望を灯す力のひとつになれば、映画は本当に喜んでくれているのではないかなと思っていますし、実際に、私は今年で10回目になるのですが、自主制作映画のコンテストは10回目で、映画祭自体は16回目ということで、私も全国色々なところの映画祭に行きますけれども、この続けるということが本当に大変なのですね。やめるのは簡単なのですが。だから、私も、去年、今年と、映画祭をやめちゃうんじゃないかな、と、実は凄くドキドキしていたのですが、特に自主制作映画という、映画のビジネスということではない、お金儲け主義では全くないところで、賞金のことだけではないですけれども、副賞も美味しい上田の信州ハムですとか、美味しいものセットを、映画を創るときはお腹も空きますので、皆さんが映画を創る際に少しでもお腹の足しになればということで、こちらのスタッフの方も考えていただいているのですけれども、何か、そういう拝金主義ではない、映画の心の部分を、この上田の映画祭の方たちは、本当に考えてくださっているのだなということが、今年で10回目ということで、去年からの1年間を振り返っても、本当に、今年62本もの応募作品があったということが、こんなに大変なときに、こんなにたくさんの応募をしてくれたというのが、感動というか感謝の気持ちでいっぱいで、これは、こういうバックグラウンド、心を育てるという上田のバックグラウンドが背景としてあったからじゃないかなと思っています。」
この言葉を受けて「今日は、映画祭のスタッフはもちろんですが、市長もお二人のお言葉を聞いて、映画祭を当分続けないといけないな、という義務感にかられていると思います。」と気を引き締める司会者。
「継続するということが一番大事なのです。やめてしまうと、そこで歴史が止まりますが、それだけではない。過去になってしまうのです。これは、過去にしないで、いつまでも未来を見続けるということが大事で、今日も、私があそこから見ていたら、若い監督さんが表彰を受けていましたが、この人たちが未来の映画を創るのです。未来の映画の歴史を産む人たちなのです。映画の物語に立っているということですね。逆に、今日、この場に立った人たちは、そのことから、「よし、未来の世界の映画は僕がやる」という自覚をもってほしいし、同時に上田の皆さんは、未来につながる人たちを送り出したということです。僕なんかは、ドキドキしながら見ていました。僕はお爺ちゃんだから、頑張ってもあと30年しかないなぁ、と(笑)。新藤監督は、100歳まででしたから、そこまでは目標にしなくてはならない。そうすると、彼らはあと80年は映画を創れるなぁ、と。80年もこれから映画を創ったら、凄いことになりますよ。あなた方自身も、自分でもびっくりするような成長をしますよ。その第一歩が、ここから始まっているということの意味。だから持続しないといけないのですね。」
「本当に、第一回目の自主映画祭のときは、お客様も関係者やゲストの方が多かったのですね。でも、その中に、入江監督がいて、いまは『サイタマノラッパー』という素晴らしい作品を創っているのですが、その入江君が一番最初のときで、ずらっと壇上に並んだときに、お客さんはたぶんスタッフの方が多かったのでしょうけれども、でも、そこから出発して、今は全国区でやっていて、実は、この度、今日これから上映させていただく『この空の花~長岡花火物語』がTAMA映画祭で優秀賞をいただいたのですけれども、そこでも『サイタマノラッパー』は同列で並んでいます。ここで出発した作家さんが、そうやってそこまで大きく、入江君だけに限らず、本当に色々な方がここから飛び出て行っていますので、ぜひぜひ皆さん、若い方は本当に大変なので、応援してあげていただきたいなと思います。」と付け加える千茱萸さん。

「入江君が10年前のここで賞をもらって、この間、日本の映画監督をまとめた本が出ましたが、僕は年寄りだから、前の方のページに乗っていますけれども、入江君も同じ本に載っている。多分、いま読む読者からすれば、入江は良いことを言っているなぁ。大林というお爺ちゃんはあんなことを言っているのか、と、僕の方が脇役になっていますよ。もう、そういう時代なのだから、それがこの10年の歴史です。上田の10年の歴史で、それを作ったということは、凄いことです。今日、僕はこの会場の熱気にびっくりしました。」
と、続けることの大切さを伝えるお二人のお言葉に
「今日は、若い人たちにもたくさん来ていただいているので、ぜひ、いまのお二人のお言葉をエネルギーにして、80年ということですから、ずっと情熱を持ち続けていただきたいですね。」と司会者。
続いて、この日上映された『淀川長治物語・神戸篇 サイナラ』など監督ご自身の作品を引き合いに出して-
「今日観てくださったこの上田で撮影した『淀川長治物語・神戸篇 サイナラ』という映画も、淀川長治さんのことを画いたものですが、これは元々、テレビのドラマとして出発したものなのですね。でも、その予算ではとても創れなかった。それで、うちの恭子さんが、これは自主映画で創ってしまって、創った映画をテレビでオンエアしてもらいましょうよ、と、自主映画ということで、こんな機械1台で編集したのですよ。CGも何も使うお金なんてありませんからね。しかも、合成用のキャメラなんてないから、揺れているのね。でも、これはプロの世界では、揺れているぞ、と言われて使えない。テレビ局だったら、そんなものは使わせてもらえないけれども、淀川さんが現役だったころにあった機材で創ろうということをひとつの思想としている訳で、これは自主映画だからできるのですね。だから、上田にロケに来て、合成がたくさんあるのだけれども、お金がないから、ベニヤ板にグリーンを塗って、それをその辺にまき散らしてね、プロの方だったらこんなものは撮りませんよ、とプロのカメラマンだったら言うだろうというような状況の中で、あれだけのものを創ってしまう。『HOUSE ハウス』がそうでしょう。今日、この後上映する『この空の花~長岡花火物語』というのも、自主映画です。いま話したTAMA映画祭や、嬉しいのは、木下惠介監督が今年で生誕100年ですが、今度、はままつ映画祭で木下さんが戦争中に創られた『陸軍』という映画と『この空の花~長岡花火物語』を2本立てで上映してくださる。あるいは、文科省が日本映画の1本として韓国で上映をしてくださる。この作品が、そのような評価を受けてきている訳ですが、これも自主映画です。もちろん、テレビ局や色々なところも協力してくれていますが、それだけでは成り立ちません。長岡というまちの市民が、老後のためにと蓄えておいたお金までも投じてくれた。だから、長岡市民の自主映画であり、それをうちの恭子さんがプロデュースするという。我々の家族だけでやっている小さな自主映画のプロダクションが手伝って、そして、それを上映する。そうすると、今日も長岡の市長代理の人が、ここに来ちゃっているという。そう言えば、長岡の森民夫市長が、いま全国市長会の会長さんをやられていて、当時の母袋市長が副会長をされていましたね。それに『22才の別れ』では、前市長会会長の大分県臼杵市の後藤市長が出演しているのですね。別に、私はそのようなことを組み合わせてはいませんよ。私が創りたい映画を、創りたいように創ったら、そのまちの市長さんが、あるいは、そういう市長さんを選んだ市民の人たちが、みんな素晴らしい人たちだということを映画が証明してくれるということですね。」
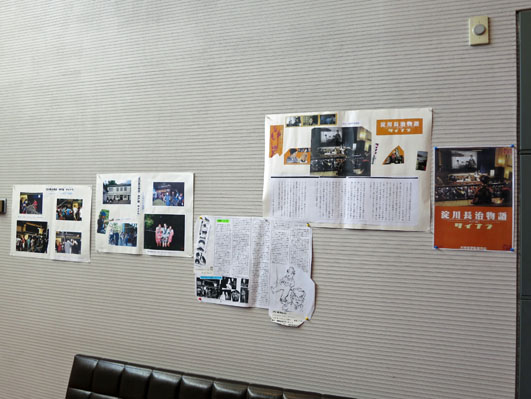
(会場内には、『淀川長治物語・神戸篇 サイナラ』のロケ当時を紹介するコーナーもありました。中には、今や大女優となった宮崎あおいさんがまだ中学生だったころの懐かしい写真も。)
「今日は、大林宣彦監督の映画を『淀川長治物語・神戸篇 サイナラ』、『HOUSE ハウス』、そして最新作の『この空の花~長岡花火物語』ということですから、今日いらっしゃった皆さんは、色々とターニングポイントとなるような映画を全て観られるということで、本当に幸運ですね。」と話す司会者。
「特に、自主映画ということで、私たちは自主映画のベテランですから、いまは企業の映画だから企業の映画を創るという時代でもないですしね。山田洋次さんという方は、いま日本でほとんど一人か二人しか残っていない映画監督ですね。松竹の映画監督ですが、僕らは、そういう意味での映画監督ではないですから。その山田洋次さんが、松竹の正月映画として予定をされていた『東京家族』という映画ですが、あの3・11のときに私は洋次さんから電話をもらいました。「大林さん、3・11前に描いたシナリオでそのまま映画を創ったらダメですよね。僕はこれをやめて、1年休んで、それから創ります。実は、『東京家族』という物語を、3・11以降にもう一度見直したのです。そうしたら、あれは全カットに戦争が映っていました。小津安二郎さんは、戦争の中で映画を創ったり断念してきたりしてきた先輩だから、全部そういう想いが映っているのです。僕らは、そういうことには気付かない。山田さんは、3・11以降にそれに気が付かれて、「大林さん、僕が今度創る『東京家族』には、全カットに放射線が映っていなくてはいけませんね。そのために、僕は1年待ちますよ。」と。松竹の映画監督である山田洋次さんも、そういう自主映画の精神で撮られたから、今度の『東京家族』は、今までの山田洋次作品を超える素晴らしい作品になっているのではないかと思っています。制作が松竹ではないですよね。東京家族製作委員会となっていますよね。黒澤さんだって、東宝を辞めて晩年は自主映画になったでしょう。新藤兼人さんも、松竹を辞めて、自主映画だからこそ、『1枚のハガキ』のような自由奔放な芸術性の高い作品を創られた。そこをいくと、今日デビューされた人たちは、最初から自主映画という商売人ではなく芸術家である訳ですから。さて、芸術とは何か。それは、今日ここに来るときに僕が見た紅葉です。「芸術の秋だね」と僕が言ったとき、恭子さんが、「秋が芸術なのよね」と言いました。雲が綺麗でしたが、雲は気象とか色々なところからできるものだけれども、僕たちから見ると、象の形をしていたり、麒麟の形をしていたり、芸術なのですね。「雲は天才である」と言いましたね。つまり、より人間的であると言うことが芸術なのですね。そのためにも、これからデビューする映画作家には、風のため、名誉のためではなく、人間のため、世界の未来の平和のために、映画を創っていくということを決心するのが、3・11以降の私たちの努めだというように思います。」と大林監督。

(りょう)
つづく
高田世界館さんにて映画『転校生』上映
『野のなななのか』TAMA映画賞・最優秀作品賞受賞!
エキストラ虎の巻
おめでとう☆彡
映画『月とキャベツ』上映&トークイベント開催決定!
銀映館ふたたび~世界館で『シグナル-月曜日のルカ』上映!
『野のなななのか』TAMA映画賞・最優秀作品賞受賞!
エキストラ虎の巻
おめでとう☆彡
映画『月とキャベツ』上映&トークイベント開催決定!
銀映館ふたたび~世界館で『シグナル-月曜日のルカ』上映!
2013年01月19日 Posted byひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。










