信州ロケ地情報
自然が美しい信州。
新緑の5~6月の頃は私がもし監督でしたらその美しさをフィルムに閉じ込めたいと願います。
さて長野県のロケ情報を二つ。
1つは撮影が先日終わった上伊那郡飯島町でロケが行われていた
冨永まい監督、柴咲コウさん主演の映画「食堂かたつむり」。
2010年公開の予定です。
詳しくは
信州ライブオン 飯島町で映画「食堂かたつむり」ロケ
「自然と一体感ある撮影に」 ←こちらをクリック下さい☆
もう1つは現在長野松竹相生座・ロキシーさんで上映中の
諏訪地方ロケ作品映画『ひぐらしのなく頃に 誓』。
昨年秋にエキストラ募集があり、撮影がありました。
諏訪圏フイルムコミッション様 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆
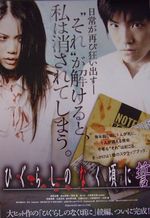
新緑の5~6月の頃は私がもし監督でしたらその美しさをフィルムに閉じ込めたいと願います。
さて長野県のロケ情報を二つ。
1つは撮影が先日終わった上伊那郡飯島町でロケが行われていた
冨永まい監督、柴咲コウさん主演の映画「食堂かたつむり」。
2010年公開の予定です。
詳しくは
信州ライブオン 飯島町で映画「食堂かたつむり」ロケ
「自然と一体感ある撮影に」 ←こちらをクリック下さい☆
もう1つは現在長野松竹相生座・ロキシーさんで上映中の
諏訪地方ロケ作品映画『ひぐらしのなく頃に 誓』。
昨年秋にエキストラ募集があり、撮影がありました。
諏訪圏フイルムコミッション様 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆
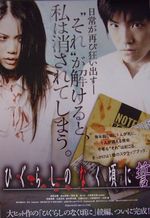
2009年07月11日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │映画 大林宣彦監督 長野
川越アフターリポート~スカラ座からキネマへ~ その4
川越アフターリポート ~In the wings スカラ座からキネマへ~ その4
【菓子屋横丁】

菓子屋横丁は、江戸時代の末期から明治時代の初めごろに、
江戸っ子好みの気取らない菓子を製造したのが始まりといわれています。
関東大震災で大きな被害を受けた東京に代わって全国への製造供給を賄い、
昭和初期には、約70軒が軒を連ねていました。
現在は、25軒ほどのお店が元気な声を響かせています。

(お菓子だけでなく…)
【第六番 見立寺(布袋尊)】

寿昌山了心院と号し、浄土宗に属します。
永禄元年、小田原北条氏の重臣で川越の城将大道寺正政繁候が、
感誉存貞上人を招き開山されました。
堂前のつげの古木の下に、徳本行者の名号碑と古誌に記されている石灯籠があります。
見立寺は、文政11年、天保11年との2度の火災にあっており、
現本堂は、明治14年に建立されたものです。

(布袋尊)

(新河岸川沿いを歩いていきます。爽やかな風が吹き抜けます。)

(町中に古い家なみが自然にとけ込んでいます。)

【第七番 妙昌寺(弁財天)】

永和元年池上本門寺第四世日山上人に開創され、
諸堂は、今の幸町周辺にありましたが、
江戸時代に松平伊豆守が川越城を改修するにあたり
城下町整備により、現在地に移ったものです。
当山の弁天さまは、遠く室町時代に時の地頭が、経文を小石に書き写し塚を築いて、
社を建てたもので、のちに川越城築城に際し、城の裏鬼門にあたるところから
太田道灌公も特に尊崇が厚かったと伝えられています。

(弁財天)
これにて、川越七福神めぐりは終了です。
さて、この日は川越駅前から伸びるクレアモール商店街内にある
『鏡山酒造跡地』オープンの日。

(告知ポスター)
鏡山酒造は、明治8年創業。平成12年に廃業するまで、
川越に「鏡山」「小江戸」などの銘柄で知られた造り酒屋でした。
品質本位の経営方針で一時は大吟醸が日本航空のファーストクラスで
振舞われていたこともあったそうです。
また、約3,000㎡の敷地には、保存価値のある白壁塗りの蔵や
市の指定保存樹木に指定されているクスノキなどが残されています。
(現在の「鏡山」は、蔵の街に酒蔵が無くなってしまったことに危機感をいだいた市民の力によって、
平成19年およそ6年ぶりに「小江戸鏡山酒造」が事業を引き継いだものです。)

(小江戸鏡山酒造のお酒)
川越市が中心となって観光の情報拠点となるよう改修を進め、
NHK連続テレビ小説『つばさ』の放送にあわせて5月2日オープンを迎えました。
来週に続く
りょう
【菓子屋横丁】
菓子屋横丁は、江戸時代の末期から明治時代の初めごろに、
江戸っ子好みの気取らない菓子を製造したのが始まりといわれています。
関東大震災で大きな被害を受けた東京に代わって全国への製造供給を賄い、
昭和初期には、約70軒が軒を連ねていました。
現在は、25軒ほどのお店が元気な声を響かせています。
(お菓子だけでなく…)
【第六番 見立寺(布袋尊)】
寿昌山了心院と号し、浄土宗に属します。
永禄元年、小田原北条氏の重臣で川越の城将大道寺正政繁候が、
感誉存貞上人を招き開山されました。
堂前のつげの古木の下に、徳本行者の名号碑と古誌に記されている石灯籠があります。
見立寺は、文政11年、天保11年との2度の火災にあっており、
現本堂は、明治14年に建立されたものです。
(布袋尊)
(新河岸川沿いを歩いていきます。爽やかな風が吹き抜けます。)
(町中に古い家なみが自然にとけ込んでいます。)
【第七番 妙昌寺(弁財天)】
永和元年池上本門寺第四世日山上人に開創され、
諸堂は、今の幸町周辺にありましたが、
江戸時代に松平伊豆守が川越城を改修するにあたり
城下町整備により、現在地に移ったものです。
当山の弁天さまは、遠く室町時代に時の地頭が、経文を小石に書き写し塚を築いて、
社を建てたもので、のちに川越城築城に際し、城の裏鬼門にあたるところから
太田道灌公も特に尊崇が厚かったと伝えられています。
(弁財天)
これにて、川越七福神めぐりは終了です。
さて、この日は川越駅前から伸びるクレアモール商店街内にある
『鏡山酒造跡地』オープンの日。
(告知ポスター)
鏡山酒造は、明治8年創業。平成12年に廃業するまで、
川越に「鏡山」「小江戸」などの銘柄で知られた造り酒屋でした。
品質本位の経営方針で一時は大吟醸が日本航空のファーストクラスで
振舞われていたこともあったそうです。
また、約3,000㎡の敷地には、保存価値のある白壁塗りの蔵や
市の指定保存樹木に指定されているクスノキなどが残されています。
(現在の「鏡山」は、蔵の街に酒蔵が無くなってしまったことに危機感をいだいた市民の力によって、
平成19年およそ6年ぶりに「小江戸鏡山酒造」が事業を引き継いだものです。)
(小江戸鏡山酒造のお酒)
川越市が中心となって観光の情報拠点となるよう改修を進め、
NHK連続テレビ小説『つばさ』の放送にあわせて5月2日オープンを迎えました。
来週に続く
りょう
2009年07月10日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ
川越アフターリポート~スカラ座からキネマへ~ その3
川越アフターリポート ~In the wings スカラ座からキネマへ~ その3
【第四番 成田山(恵比寿天)】

大本山成田山新勝寺の別院で、真言宗密教の寺院です。
ご本尊は不動明王。
交通安全祈願で広く知られ、亀のいるお不動さまとしても親しまれています。
当寺は、嘉永6年、下総の国新宿の石川照温が、廃寺となっていた本行院を
成田山新勝寺の別院として再興したのが始まりといわれています。

(恵比寿天)
商店街の通りを抜け、ここから先は、蔵造り以外にも趣のある建物が増えていきます。




(大正浪漫夢通り)

(かつて地域で賑わいを見せていたであろう映画館も、いまはひっそりと…)
【第五番 蓮馨寺(福禄寿神)】

生活に困窮していた農民たちの子供を引き取り教育した子育呑龍上人で親しまれている当山は、
天文18年川越城将大道寺駿河守政繁候の母堂蓮馨大姉が、
民衆の心の安らぎの場として創建しました。
開山は感誉存貞上人で、のち大本山増上寺第十世に登られた方でした。
徳川時代には、関東における浄土宗“十八檀林”の一つに列せられ、
幕府公認の僧侶養成機関となり、多くの学僧を育てました。
ご本尊は阿弥陀如来です。

(福禄寿神)
【蔵造りの町なみ】

(仲町交差点。ここから蔵づくりのまち並みが広がります。)
ドラマ『つばさ』の主なロケ地。
ヒロイン玉木つばさが住むとされる幸町があります。
ロケは昨年11月初めから3週間にわたり、多数の市民ボランティア協力のもと行われました。
ロケ地の情報は、後述の鏡山酒造跡地の観光案内所にて入手することができます。

(時の鐘)
続く
りょう
【第四番 成田山(恵比寿天)】
大本山成田山新勝寺の別院で、真言宗密教の寺院です。
ご本尊は不動明王。
交通安全祈願で広く知られ、亀のいるお不動さまとしても親しまれています。
当寺は、嘉永6年、下総の国新宿の石川照温が、廃寺となっていた本行院を
成田山新勝寺の別院として再興したのが始まりといわれています。
(恵比寿天)
商店街の通りを抜け、ここから先は、蔵造り以外にも趣のある建物が増えていきます。
(大正浪漫夢通り)
(かつて地域で賑わいを見せていたであろう映画館も、いまはひっそりと…)
【第五番 蓮馨寺(福禄寿神)】
生活に困窮していた農民たちの子供を引き取り教育した子育呑龍上人で親しまれている当山は、
天文18年川越城将大道寺駿河守政繁候の母堂蓮馨大姉が、
民衆の心の安らぎの場として創建しました。
開山は感誉存貞上人で、のち大本山増上寺第十世に登られた方でした。
徳川時代には、関東における浄土宗“十八檀林”の一つに列せられ、
幕府公認の僧侶養成機関となり、多くの学僧を育てました。
ご本尊は阿弥陀如来です。
(福禄寿神)
【蔵造りの町なみ】
(仲町交差点。ここから蔵づくりのまち並みが広がります。)
ドラマ『つばさ』の主なロケ地。
ヒロイン玉木つばさが住むとされる幸町があります。
ロケは昨年11月初めから3週間にわたり、多数の市民ボランティア協力のもと行われました。
ロケ地の情報は、後述の鏡山酒造跡地の観光案内所にて入手することができます。
(時の鐘)
続く
りょう
2009年07月09日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ
川越アフターリポート~スカラ座からキネマへ~ その2
川越アフターリポート ~In the wings スカラ座からキネマへ~ その2

(それでは、川越駅を出発しましょう)
【第一番 妙善寺(毘沙門天)】

天台宗に属する元中院の末寺で、道人山三心院と呼ばれています。
尊能法印が寛永元年に建立、堂宇は天明8年の大火によって焼失して以降、
仮堂でしたが、昭和53年に再建されました。
創建時のご本尊は薬師如来でしたが、現在のご本尊は不動明王で智証大師の作。
脇に阿弥陀如来、観世音菩薩、毘沙門天を安置しています。

(毘沙門天)

(境内にはさつまいも地蔵尊も。
川越と言えば、サツマイモと言われるほどイモの町としても有名で、
その歴史は250年以上あります。
寛政の頃、江戸の町に焼き芋屋が現れ、その焼き芋用のイモとして、
「川越いも」は発展し有名になったそうです。)
【第二番 天然寺(寿老人)】

自然山大日院と号し、本尊大日如来を安置。
日本最初の大師号であり、マルコポーロの東方見聞録や西遊記と比される
『入唐求法巡礼行記』の著者としても有名な慈覚大師円仁草創の地とも伝えられていますが、
天文23年9月栄海上人によって創建されました。
境内には願掛観音像、六地蔵尊等があります。
当地の寿老人は、彦根智教寺に安置されていたものです。

(寿老人)
【中院】

後述の喜多院とともに天長7年慈覚大師によって創立。
元来星野山無量寿寺のなかに北院・中院・南院の3院があり、
それぞれが仏蔵院、仏地院、多聞院と称していたものです。
喜多院に天海僧正が来住する以前は、むしろ中院の方が勢力を持っていました。
境内には、河越茶・狭山茶の起源の碑があります。
【仙波東照宮】

徳川家康の遺骸を久能山から日光に移葬した際、喜多院に4日間逗留して供養したことから、
天海僧正が寛永10年この地に創建しました。
当初から独立した社格をもたず、喜多院の一隅に造営されたもので、
日光東照宮、久能山の東照宮とともに三大東照宮といわれています。

(境内は、多部さん&写真家・佐内さんのお気に入りの場所でもあります。)
【第三番 喜多院(大黒天)】

先日のスカラ座レポートでも、しげぞーさんのまち巡りのなかで紹介していただきましたね。
天長七年、淳和天皇の勅で慈覚大師円仁により創建された
星野山無量寿寺が始まりとされる喜多院。
寛永15年川越大火で焼けた際、将軍徳川家光公が
江戸城内の「徳川家光誕生の間」を書院、
「春日局化粧の間」を客殿として移築し、その他諸堂を再建しました。
すべて文化財で拝観ができます。
毎日厄除けなどの護摩修法も行われています。

(大黒天)
続く
りょう
(それでは、川越駅を出発しましょう)
【第一番 妙善寺(毘沙門天)】
天台宗に属する元中院の末寺で、道人山三心院と呼ばれています。
尊能法印が寛永元年に建立、堂宇は天明8年の大火によって焼失して以降、
仮堂でしたが、昭和53年に再建されました。
創建時のご本尊は薬師如来でしたが、現在のご本尊は不動明王で智証大師の作。
脇に阿弥陀如来、観世音菩薩、毘沙門天を安置しています。
(毘沙門天)
(境内にはさつまいも地蔵尊も。
川越と言えば、サツマイモと言われるほどイモの町としても有名で、
その歴史は250年以上あります。
寛政の頃、江戸の町に焼き芋屋が現れ、その焼き芋用のイモとして、
「川越いも」は発展し有名になったそうです。)
【第二番 天然寺(寿老人)】
自然山大日院と号し、本尊大日如来を安置。
日本最初の大師号であり、マルコポーロの東方見聞録や西遊記と比される
『入唐求法巡礼行記』の著者としても有名な慈覚大師円仁草創の地とも伝えられていますが、
天文23年9月栄海上人によって創建されました。
境内には願掛観音像、六地蔵尊等があります。
当地の寿老人は、彦根智教寺に安置されていたものです。
(寿老人)
【中院】
後述の喜多院とともに天長7年慈覚大師によって創立。
元来星野山無量寿寺のなかに北院・中院・南院の3院があり、
それぞれが仏蔵院、仏地院、多聞院と称していたものです。
喜多院に天海僧正が来住する以前は、むしろ中院の方が勢力を持っていました。
境内には、河越茶・狭山茶の起源の碑があります。
【仙波東照宮】
徳川家康の遺骸を久能山から日光に移葬した際、喜多院に4日間逗留して供養したことから、
天海僧正が寛永10年この地に創建しました。
当初から独立した社格をもたず、喜多院の一隅に造営されたもので、
日光東照宮、久能山の東照宮とともに三大東照宮といわれています。
(境内は、多部さん&写真家・佐内さんのお気に入りの場所でもあります。)
【第三番 喜多院(大黒天)】
先日のスカラ座レポートでも、しげぞーさんのまち巡りのなかで紹介していただきましたね。
天長七年、淳和天皇の勅で慈覚大師円仁により創建された
星野山無量寿寺が始まりとされる喜多院。
寛永15年川越大火で焼けた際、将軍徳川家光公が
江戸城内の「徳川家光誕生の間」を書院、
「春日局化粧の間」を客殿として移築し、その他諸堂を再建しました。
すべて文化財で拝観ができます。
毎日厄除けなどの護摩修法も行われています。
(大黒天)
続く
りょう
2009年07月08日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ
川越アフターリポート~スカラ座からキネマへ~ その1
川越アフターリポート ~In the wings スカラ座からキネマへ~ その1
『転校生さよならあなた日記』では善光寺御開帳に合わせて、
善光寺門前町の七福神を紹介させていただきました。
そして、現在放映中のNHK連続テレビ小説『つばさ』の舞台、
小江戸・川越のまちにも七福神がいます。

(川越七福神めぐりパンフレット)
今回は、だいぶ経ってしまいましたが、
先日の川越スカラ座のアフターレポートとして、川越の七福神を皆さまと共に巡りながら、
あらためて川越のまちの魅力を紹介したいと思います。
『川越スカラ座から川越キネマへ』
それでは、“つばさ”のまちに、take off!!


(電車もつばさ一色に)

(川越駅ホームに並ぶポスター)
川越のまち歴史については、先日のレポートでしげぞーさんにも
紹介していただきましたが、おさらいも兼ねてもう一度。
川越市は、埼玉県の中央南部に位置し、人口約33万人。
大正11年に埼玉県内で初めて市制が施行されました。
遠く平安時代には、桓武平氏の流れをくむ武蔵武士の河越氏が館を構え、
勢力を伸ばしていた土地です。
川越は、一名「江戸の母」ともいわれ、かつては大江戸(現東京)に対し
“小江戸”と呼ばれていたように、川越藩の城下町として隆盛を極めた所でした。
川越と江戸とは川越街道、新河岸川の舟運といった大動脈で結ばれ、
城下は周辺農村地帯の物資の集積地として大変賑わいをみせていました。
川越商人は、これらの物資を大消費地江戸に供給したりすることで
多くの富を蓄積することとなりました。
とりわけその中心となったのが現在の一番街、
仲町から札の辻にかけての蔵造りの通り筋で、大店が何軒も軒を並べていました。
しかし、当時は蔵造りの建物が町内に何軒も建っていたわけではありませんでした。
倉庫としての土蔵は、すでに数多く建ってはいましたが、
お店は石置きの杉皮葺屋根の家が多かったと考えられています。
川越に多くの蔵造りが生まれたのは、明治26年の川越大火を契機としています。
この火事は、町全体の3分の1以上である1,300余戸を焼失するという大きなものでした。
川越の商人は町の復興にあたり、耐火建築としては、
当時西洋から入ってきたレンガ造りも既にありましたが、
日本の伝統的な耐火建築である土蔵造りを採用しました。
そして、黒漆喰で壁を鏡のように磨き上げたのです。
現在、ドラマではヒロイン玉木つばさたちが暮らす町として登場する
幸町を中心とした23件が文化財に指定されています。

(訪れた日、玉木つばさが住む町“幸町”のお囃子も)
川越は、本場の江戸(東京)ではすでに消滅してしまった蔵造りのまち並みをはじめとして、
埼玉りそな銀行舎などのレンガ造りの洋風建築や寺社建築など
様々な時代の建築が重層して活きているまちです。

(埼玉りそな銀行舎)
そんな『小江戸川越七福神めぐり』は、全行程6km。
川越駅を起点にゆっくり徒歩でも半日でひと回り、観光と健康増進を兼ねた手ごろなコースです。
途中、中院や仙波東照宮などの歴史的な寺社を始め、大正浪漫夢通りや蔵造りの一番街、
菓子屋横丁などのまち並み、また新河岸川の川辺など、
「15分では観られない」“日常のなか”の川越を満喫することができるコースです。
続く
りょう
『転校生さよならあなた日記』では善光寺御開帳に合わせて、
善光寺門前町の七福神を紹介させていただきました。
そして、現在放映中のNHK連続テレビ小説『つばさ』の舞台、
小江戸・川越のまちにも七福神がいます。
(川越七福神めぐりパンフレット)
今回は、だいぶ経ってしまいましたが、
先日の川越スカラ座のアフターレポートとして、川越の七福神を皆さまと共に巡りながら、
あらためて川越のまちの魅力を紹介したいと思います。
『川越スカラ座から川越キネマへ』
それでは、“つばさ”のまちに、take off!!
(電車もつばさ一色に)
(川越駅ホームに並ぶポスター)
川越のまち歴史については、先日のレポートでしげぞーさんにも
紹介していただきましたが、おさらいも兼ねてもう一度。
川越市は、埼玉県の中央南部に位置し、人口約33万人。
大正11年に埼玉県内で初めて市制が施行されました。
遠く平安時代には、桓武平氏の流れをくむ武蔵武士の河越氏が館を構え、
勢力を伸ばしていた土地です。
川越は、一名「江戸の母」ともいわれ、かつては大江戸(現東京)に対し
“小江戸”と呼ばれていたように、川越藩の城下町として隆盛を極めた所でした。
川越と江戸とは川越街道、新河岸川の舟運といった大動脈で結ばれ、
城下は周辺農村地帯の物資の集積地として大変賑わいをみせていました。
川越商人は、これらの物資を大消費地江戸に供給したりすることで
多くの富を蓄積することとなりました。
とりわけその中心となったのが現在の一番街、
仲町から札の辻にかけての蔵造りの通り筋で、大店が何軒も軒を並べていました。
しかし、当時は蔵造りの建物が町内に何軒も建っていたわけではありませんでした。
倉庫としての土蔵は、すでに数多く建ってはいましたが、
お店は石置きの杉皮葺屋根の家が多かったと考えられています。
川越に多くの蔵造りが生まれたのは、明治26年の川越大火を契機としています。
この火事は、町全体の3分の1以上である1,300余戸を焼失するという大きなものでした。
川越の商人は町の復興にあたり、耐火建築としては、
当時西洋から入ってきたレンガ造りも既にありましたが、
日本の伝統的な耐火建築である土蔵造りを採用しました。
そして、黒漆喰で壁を鏡のように磨き上げたのです。
現在、ドラマではヒロイン玉木つばさたちが暮らす町として登場する
幸町を中心とした23件が文化財に指定されています。
(訪れた日、玉木つばさが住む町“幸町”のお囃子も)
川越は、本場の江戸(東京)ではすでに消滅してしまった蔵造りのまち並みをはじめとして、
埼玉りそな銀行舎などのレンガ造りの洋風建築や寺社建築など
様々な時代の建築が重層して活きているまちです。
(埼玉りそな銀行舎)
そんな『小江戸川越七福神めぐり』は、全行程6km。
川越駅を起点にゆっくり徒歩でも半日でひと回り、観光と健康増進を兼ねた手ごろなコースです。
途中、中院や仙波東照宮などの歴史的な寺社を始め、大正浪漫夢通りや蔵造りの一番街、
菓子屋横丁などのまち並み、また新河岸川の川辺など、
「15分では観られない」“日常のなか”の川越を満喫することができるコースです。
続く
りょう
2009年07月07日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ
おのみちまちあるき。。。第49話「これが噂の・・<↓山>。」
おのみちまちあるき。。。第49話「これが噂の・・・<↓山>。」
お寺なのに鳥居?鳥居は神社のシンボルでは・・・という「?」がつきますが、
これが古来の日本の信仰を表す1つのかたちなのかもしれません。
ただ1つの「絶対神」がいて、従うか逆らうかで
正邪・善悪を判断する「一神教」文化と異なり、
日本では、自然現象から草花、道具にまでこの世界に存在する
全てのものに「八百万の神」が宿るという、
個性尊重の「多神教」文化が根付いていました。
七五三やお宮参り、正月の初詣では神社におまいりし、
教会で結婚式をあげ、人生の最後にはお寺でお経を上げてもらい・・・
こんな混沌とした何でもあり、な発想は、
よいものはなんでも吸収し、「みんなちがって、みんな、いい」
(By女流詩人:金子みすゞさん)な発想と文化を持つ日本人ならではでしょう。
そういう発想のなかでは、日本古来の神も、
大陸から伝来した仏もそれほど違いがなかったと。
(人間が亡くなって仏になり、神になるという発想は、一神教文化ではありえないそうです。
神は神、人間はどう頑張ってもその忠実な弟子であり使徒と。)

深山幽谷で俗世界を離れ修行をする山伏は仏教ですが、
古来、山を神として崇めた文化と融合しているところもあるのでしょう。
ここ瑠璃山も、仏教的には奥の院があり「極楽浄土」なのですが、
神道的には山そのものがご神体ということになります。
鳥居の手前にあった「心」と書かれた石。
「心」と書かれていた裏側には
「↓山」。
赤ペンキの単なる落書きではありません。
よくみれば少し彫り込まれて、そこに色を載せてはっきりさせていることが分かります。

これこそ、山そのものが昔から<ご神体>であった名残でしょう。
(2階建ての家の1階に神棚があり、階上にも部屋がある場合、
神棚上の天井に<空><天>と書いた紙を貼ります。
神様よりも上に人間がいては畏れ多い・・・、ということで、
その上は別世界、と宣言するようなものです。
ここでは逆に、山頂に行くにはどうしても「神様」の上を人間が歩き、
足でご神体を踏みつけてゆくしかないので、「ここから下は山:聖域⇔上が人間界」
と宣言しているのでしょう。

鳥居を過ぎて少しゆくといよいよ不動岩。
壁面に不動明王のお姿が彫り込まれています。
この場所、断崖絶壁に近いです。へたに崖下を覗きこむと足がすくみます。
よそで作って持ち込んだわけではなく、まさにここで彫ったのです。
尾道石工の高い技術と度胸には脱帽するしかありません。
(高層ビルの頂上近くで作業するようなもの。
平地で平静な精神状態ならばできることも、そんな高所で力を100%発揮するのは
並大抵のことではないですよね)

不動岩の上部、右奥に手すりがみえますが、
岩の下からまわりこむと岩の上にあがることができます。
映画「ふたり」で実加が神永青年のプロポーズをお断りした場所。
足はすくみますが、絶景が眼下に広がり、
ここまでのぼってきた疲れもすっかり吹っ飛んでしまうのでした。
(この風景も、自然の造形と人間の営みが見事に融合したもの。
それを、はるか天上の聖域から俯瞰している錯覚まで覚えるのです^^)


49回(!)に渡って「転校生 さよならあなた日記」の貴重なスペースをお借りし、
大林監督作品つながりの尾道について一貫性もなく書き綴ってしまいました。
映画とともに「まちあるき」「路地の魅力」についても
話題にしたブログなのでぜひ、
というひがしざわさまのお言葉をいただき、
気軽に始めたこのシリーズ、
こんなに大作になるとは思ってもおりませんでした。
思いつくまま乱筆・脱線ばかりの尾道紀行、
長きにわたりおつきあいいただき、
ありがとうございました。
そしてなにより、記事の掲載にあたって貴重なスペースを
ご提供いただいたひがしざわさま、感謝です。
信州長野も歴史あるエリア。
歩き回ればちょっとした町の風景、小さなものにも同じように
歴史やいわれがあることでしょう。
ぜひ、「みすずかる・・・信州ながのまちあるき」を読んでみたいものです♪
(それは全国どこの土地や町にもいえることです。それぞれの土地土地について
改めて見直すことで、魅力に気づき愛着も湧いて活性化につながると思います)
え?49話とは中途半端、
もう1話で50話完結!
どうしてしないのかって?
御袖天満宮の石段に1箇所だけ継ぎ目があるのと同じ、
完全なものはあとは滅びるだけだから・・・の物まねではありませんよ。
どこの街の風景も、1人1人、それぞれに見え方が違うのです。
そう、もう1話は、ぜひ皆様が実際に訪れて、ご自分の目で見つけてください^^。
こうして街の物語はまた始まるのです。
(完)
しげぞー
お寺なのに鳥居?鳥居は神社のシンボルでは・・・という「?」がつきますが、
これが古来の日本の信仰を表す1つのかたちなのかもしれません。
ただ1つの「絶対神」がいて、従うか逆らうかで
正邪・善悪を判断する「一神教」文化と異なり、
日本では、自然現象から草花、道具にまでこの世界に存在する
全てのものに「八百万の神」が宿るという、
個性尊重の「多神教」文化が根付いていました。
七五三やお宮参り、正月の初詣では神社におまいりし、
教会で結婚式をあげ、人生の最後にはお寺でお経を上げてもらい・・・
こんな混沌とした何でもあり、な発想は、
よいものはなんでも吸収し、「みんなちがって、みんな、いい」
(By女流詩人:金子みすゞさん)な発想と文化を持つ日本人ならではでしょう。
そういう発想のなかでは、日本古来の神も、
大陸から伝来した仏もそれほど違いがなかったと。
(人間が亡くなって仏になり、神になるという発想は、一神教文化ではありえないそうです。
神は神、人間はどう頑張ってもその忠実な弟子であり使徒と。)
深山幽谷で俗世界を離れ修行をする山伏は仏教ですが、
古来、山を神として崇めた文化と融合しているところもあるのでしょう。
ここ瑠璃山も、仏教的には奥の院があり「極楽浄土」なのですが、
神道的には山そのものがご神体ということになります。
鳥居の手前にあった「心」と書かれた石。
「心」と書かれていた裏側には
「↓山」。
赤ペンキの単なる落書きではありません。
よくみれば少し彫り込まれて、そこに色を載せてはっきりさせていることが分かります。
これこそ、山そのものが昔から<ご神体>であった名残でしょう。
(2階建ての家の1階に神棚があり、階上にも部屋がある場合、
神棚上の天井に<空><天>と書いた紙を貼ります。
神様よりも上に人間がいては畏れ多い・・・、ということで、
その上は別世界、と宣言するようなものです。
ここでは逆に、山頂に行くにはどうしても「神様」の上を人間が歩き、
足でご神体を踏みつけてゆくしかないので、「ここから下は山:聖域⇔上が人間界」
と宣言しているのでしょう。
鳥居を過ぎて少しゆくといよいよ不動岩。
壁面に不動明王のお姿が彫り込まれています。
この場所、断崖絶壁に近いです。へたに崖下を覗きこむと足がすくみます。
よそで作って持ち込んだわけではなく、まさにここで彫ったのです。
尾道石工の高い技術と度胸には脱帽するしかありません。
(高層ビルの頂上近くで作業するようなもの。
平地で平静な精神状態ならばできることも、そんな高所で力を100%発揮するのは
並大抵のことではないですよね)
不動岩の上部、右奥に手すりがみえますが、
岩の下からまわりこむと岩の上にあがることができます。
映画「ふたり」で実加が神永青年のプロポーズをお断りした場所。
足はすくみますが、絶景が眼下に広がり、
ここまでのぼってきた疲れもすっかり吹っ飛んでしまうのでした。
(この風景も、自然の造形と人間の営みが見事に融合したもの。
それを、はるか天上の聖域から俯瞰している錯覚まで覚えるのです^^)
49回(!)に渡って「転校生 さよならあなた日記」の貴重なスペースをお借りし、
大林監督作品つながりの尾道について一貫性もなく書き綴ってしまいました。
映画とともに「まちあるき」「路地の魅力」についても
話題にしたブログなのでぜひ、
というひがしざわさまのお言葉をいただき、
気軽に始めたこのシリーズ、
こんなに大作になるとは思ってもおりませんでした。
思いつくまま乱筆・脱線ばかりの尾道紀行、
長きにわたりおつきあいいただき、
ありがとうございました。
そしてなにより、記事の掲載にあたって貴重なスペースを
ご提供いただいたひがしざわさま、感謝です。
信州長野も歴史あるエリア。
歩き回ればちょっとした町の風景、小さなものにも同じように
歴史やいわれがあることでしょう。
ぜひ、「みすずかる・・・信州ながのまちあるき」を読んでみたいものです♪
(それは全国どこの土地や町にもいえることです。それぞれの土地土地について
改めて見直すことで、魅力に気づき愛着も湧いて活性化につながると思います)
え?49話とは中途半端、
もう1話で50話完結!
どうしてしないのかって?
御袖天満宮の石段に1箇所だけ継ぎ目があるのと同じ、
完全なものはあとは滅びるだけだから・・・の物まねではありませんよ。
どこの街の風景も、1人1人、それぞれに見え方が違うのです。
そう、もう1話は、ぜひ皆様が実際に訪れて、ご自分の目で見つけてください^^。
こうして街の物語はまた始まるのです。
(完)
しげぞー
2009年07月06日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(1) │おのみちまちあるき
「タウンモビリティ」@長野・豆蔵
このブログでも過去にお伝えした
“N-ex Talking Over”。 ←詳しくはこちらをクリックして下さい☆
テーマに沿って参加者皆で語り合う、
長野県各地で繰り広げられてきたカフェ・ミーティングです。
ひがしざわも昨年長野市の“善光寺平の物語を創造する”というテーマに
<転校生 さよなら あなた>の話をしたい!と参加させていただきました。
2009年度、装いも新しく“N-ex Talking Over”が再び始まります。
ひがしざわも企画段階からほんのちょっぴりですが、お手伝いさせて頂きました。
企画してくださった はなしもの まぐさんにはとても感謝致します。
「タウンモビリティ」@長野・豆蔵
「タウンモビリティ」
~歩くことから、まちづくりを考える~
◎日程:2009年7月8日(水)
◎時間:19:00
◎会場:@長野市・豆蔵(長野市大門町518)
◎参加費:500円
◎ゲスト:hareさん(福祉住環境コーディネーター)
★企画者:はなしもの まぐさん
タウンモビリティとは、電動スクーターや車イスなどを
長距離の歩行が困難な人に貸し出して、
町の中を自由に移動できるようにし、まちあるきや買物などを楽しんで頂くという取組みです。
会場の豆蔵さんは使われなくなった古い土蔵を信大の学生さんが直して綺麗に掃除して、
善光寺さんの御開帳の期間はお味噌等を販売していたところです。
<転校生 さよなら あなた>のロケ地となった門前農館さんの奥にあります。
古い建物が壊されることなく再び命を吹き込まれ、
多くの方が出入りする場所になった事は素敵です。
<転校生 さよなら あなた>の映画の中でも
蓮佛美沙子ちゃんの一美<カズオ>が病院を抜け出し
車椅子に乗るシーンが出てきます。
地理的に難しいところもありますが、出来れば車椅子の方にも
ロケ地巡りを楽しんでいただく試みができたらいいねというお話を頂きました。
多くの方にまちあるきを楽しんで頂きたいです。
切り口は歴史でも映画でも買物でも、まちを歩きたいという気持ちの
入口がたくさんあるともっともっと楽しい!
皆様のご参加をお待ちしてます。

“N-ex Talking Over”。 ←詳しくはこちらをクリックして下さい☆
テーマに沿って参加者皆で語り合う、
長野県各地で繰り広げられてきたカフェ・ミーティングです。
ひがしざわも昨年長野市の“善光寺平の物語を創造する”というテーマに
<転校生 さよなら あなた>の話をしたい!と参加させていただきました。
2009年度、装いも新しく“N-ex Talking Over”が再び始まります。
ひがしざわも企画段階からほんのちょっぴりですが、お手伝いさせて頂きました。
企画してくださった はなしもの まぐさんにはとても感謝致します。
「タウンモビリティ」@長野・豆蔵
「タウンモビリティ」
~歩くことから、まちづくりを考える~
◎日程:2009年7月8日(水)
◎時間:19:00
◎会場:@長野市・豆蔵(長野市大門町518)
◎参加費:500円
◎ゲスト:hareさん(福祉住環境コーディネーター)
★企画者:はなしもの まぐさん
タウンモビリティとは、電動スクーターや車イスなどを
長距離の歩行が困難な人に貸し出して、
町の中を自由に移動できるようにし、まちあるきや買物などを楽しんで頂くという取組みです。
会場の豆蔵さんは使われなくなった古い土蔵を信大の学生さんが直して綺麗に掃除して、
善光寺さんの御開帳の期間はお味噌等を販売していたところです。
<転校生 さよなら あなた>のロケ地となった門前農館さんの奥にあります。
古い建物が壊されることなく再び命を吹き込まれ、
多くの方が出入りする場所になった事は素敵です。
<転校生 さよなら あなた>の映画の中でも
蓮佛美沙子ちゃんの一美<カズオ>が病院を抜け出し
車椅子に乗るシーンが出てきます。
地理的に難しいところもありますが、出来れば車椅子の方にも
ロケ地巡りを楽しんでいただく試みができたらいいねというお話を頂きました。
多くの方にまちあるきを楽しんで頂きたいです。
切り口は歴史でも映画でも買物でも、まちを歩きたいという気持ちの
入口がたくさんあるともっともっと楽しい!
皆様のご参加をお待ちしてます。

2009年07月05日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │まち巡り
こまねこ続編
今日は休日モードで
昨年みすずかるしなのNAGANO映画祭で上映された<こまねこ>情報を。
何と!合田監督が待望のこまねこの続編制作に取り掛かったようです。
こまねこ公式ブログ ←詳しくはこちらをクリック下さい☆
(新作のこま撮り風景も覗けます☆)
ごーだのらくがきつうしん ←詳しくはこちらをクリック下さい☆
長野松竹相生座・ロキシー様で映画の開始前の<こまねこ>のマナー広告を
映画祭を期に導入頂きましたが、あの大ヒット作<おくりびと>の前に流されました。
約1万人の来客があったそうなので(タガミさん、合ってる?)、
長野市においての<こまねこ>の知名度は抜群かもしれません。
新作もまたロキシーさんのスクリーンで会える日が来るのでしょうか!

(C)TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナーズ
昨年みすずかるしなのNAGANO映画祭で上映された<こまねこ>情報を。
何と!合田監督が待望のこまねこの続編制作に取り掛かったようです。
こまねこ公式ブログ ←詳しくはこちらをクリック下さい☆
(新作のこま撮り風景も覗けます☆)
ごーだのらくがきつうしん ←詳しくはこちらをクリック下さい☆
長野松竹相生座・ロキシー様で映画の開始前の<こまねこ>のマナー広告を
映画祭を期に導入頂きましたが、あの大ヒット作<おくりびと>の前に流されました。
約1万人の来客があったそうなので(タガミさん、合ってる?)、
長野市においての<こまねこ>の知名度は抜群かもしれません。
新作もまたロキシーさんのスクリーンで会える日が来るのでしょうか!
(C)TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナーズ
2009年07月04日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │映画関連
おのみちまちあるき。。。第48話「いざ、お山に。」 後篇
おのみちまちあるき。。。第48話「いざ、お山に。」 後篇
橋を渡るとまもなく本格的な山道に。
かなりの傾斜です。頂上近くまでこのような風景が続きます。
この先に目的地があると知らなけば、
なかなか奥へ進んでゆく「勇気」が出ませんね^^;。

沿道には33体の石仏が立ち並んでいます。
地蔵菩薩や如意輪観音菩薩、十一面観音菩薩に、先回ご紹介の六地蔵様など。
お名前とそれぞれの真言が書かれた看板が添えられています。
真言とは大日経など密教の経典にある真実の言葉という意味で、
仏の言葉を言います。
真言宗の「真言」もこれに由来。
真言は音が重要なので、翻訳せず梵語(サンスクリット)をそのまま音読します。
そういえば「日限地蔵尊」にもお地蔵様の真言が書かれていました。
確か・・・おんかかかびさんまえいそわか、でした。)
立ち並ぶ観音様、これが「観音のこみち」という名前の由来です。
無事に登頂できるよう、見守ってくださっているような、フシギな気配が漂っています。
(うっそうと暗いものの、コワくもなくて、むしろ心強く落ち着くのです)
信仰心や宗教的な背景などが特になくとも、自然と、1体ずつ通り過ぎる時には
感謝の気持ちが湧いてきて、手を合わせながらのぼってゆくことになるのでした。。


歩くことおよそ20分、ようやく空が見え、開けた場所にやってきました。
尾道の町が一望できます。
まだ8合目ですが、山麓から見えた1番上近くまで来たのですね。
林の中は山道にありがちな丸太の階段でしたが、ここまで来ると石材を組み合わせた石段や、
巨石の一部を階段状に削った場所が増えてきます。
鳥居が見えてきました。


鳥居の側の岩に「心」と刻まれています。
この鳥居が浄土寺奥の院の参道の入り口になるのです。
心を洗い、参拝しましょう。(え?お寺なのに鳥居?)
しげぞー
橋を渡るとまもなく本格的な山道に。
かなりの傾斜です。頂上近くまでこのような風景が続きます。
この先に目的地があると知らなけば、
なかなか奥へ進んでゆく「勇気」が出ませんね^^;。
沿道には33体の石仏が立ち並んでいます。
地蔵菩薩や如意輪観音菩薩、十一面観音菩薩に、先回ご紹介の六地蔵様など。
お名前とそれぞれの真言が書かれた看板が添えられています。
真言とは大日経など密教の経典にある真実の言葉という意味で、
仏の言葉を言います。
真言宗の「真言」もこれに由来。
真言は音が重要なので、翻訳せず梵語(サンスクリット)をそのまま音読します。
そういえば「日限地蔵尊」にもお地蔵様の真言が書かれていました。
確か・・・おんかかかびさんまえいそわか、でした。)
立ち並ぶ観音様、これが「観音のこみち」という名前の由来です。
無事に登頂できるよう、見守ってくださっているような、フシギな気配が漂っています。
(うっそうと暗いものの、コワくもなくて、むしろ心強く落ち着くのです)
信仰心や宗教的な背景などが特になくとも、自然と、1体ずつ通り過ぎる時には
感謝の気持ちが湧いてきて、手を合わせながらのぼってゆくことになるのでした。。
歩くことおよそ20分、ようやく空が見え、開けた場所にやってきました。
尾道の町が一望できます。
まだ8合目ですが、山麓から見えた1番上近くまで来たのですね。
林の中は山道にありがちな丸太の階段でしたが、ここまで来ると石材を組み合わせた石段や、
巨石の一部を階段状に削った場所が増えてきます。
鳥居が見えてきました。
鳥居の側の岩に「心」と刻まれています。
この鳥居が浄土寺奥の院の参道の入り口になるのです。
心を洗い、参拝しましょう。(え?お寺なのに鳥居?)
しげぞー
2009年07月03日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │おのみちまちあるき
おのみちまちあるき。。。第48話「いざ、お山に。」 前篇
おのみちまちあるき。。。第48話「いざ、お山に。」
今回のまちあるき、最終目的地がみえてまいりました。
浄土寺の脇に出ると、背後に瑠璃山(浄土寺山)がそびえています。
右側が海龍寺の石段。
改めてみると非常に高い山です。
千光寺山の千光寺と艮神社、西国寺山の西国寺などの関係と同様、
もともとはお寺や神社が山を崇めて祀る目的で山麓に建てられた、
という説にも納得できるところがあります。

頂上付近に巨石のあるのがお分かりでしょうか。
「ふたり」に登場した不動岩です。
不動岩の先には浄土寺の奥の院があり、頂上には展望台も設けられています。
(山麓の浄土寺と山頂の奥の院は、艮神社と千光寺の関係にも重なります)
裏側からぐるりと回りこみ車で頂上近くまで行くことも可能ですが、
やはりそれでは味気ないですし自分の足で歩いて登りましょう。
それにしても遠いですねぇ・・・。
道を進むと「観音のこみち」というコースで頂上まで行くことができます。
ただくれぐれも気合を入れて。
標高差からも分かるように、かなり本格的な山道の「ハイキング」です。
当然、途中には水分補給できる飲み物の自販機も、水道もありません。
体力の消耗もかなりなものですから、
1日中歩き回ってへとへとになった夕方などには入山なさりませんよう。
街灯もなく昼なお暗い山道。
日が暮れると真っ暗ですし、急な斜面や断崖などもあってとても危険です!
(ここからの夕焼けは見事なのですが・・・)
お勧めは、午前中早く、まだ体力が十分ある時分ですね^^。
さあ、いよいよ入山です。
入口には細工の凝った石橋が架かっています。
瑠璃山への入山口なので「瑠璃橋」と名前がついています。
その昔、防地川の川下にあった芝居小屋・偕楽座の前にかかっていたもの。
大正時代に木橋から石橋に架け替えられたものが、
その後道路拡張のため解体され、同じく鉄道以南にかかっていた
他の橋の石材とともに浄土寺に預けられました。
昭和に入ってその材料を使って長さ約13mの石橋を完成させ、橋名を「瑠璃橋」と改めたそうです。
石工の町・尾道ならではの遺物といえますね。

続く
しげぞー
今回のまちあるき、最終目的地がみえてまいりました。
浄土寺の脇に出ると、背後に瑠璃山(浄土寺山)がそびえています。
右側が海龍寺の石段。
改めてみると非常に高い山です。
千光寺山の千光寺と艮神社、西国寺山の西国寺などの関係と同様、
もともとはお寺や神社が山を崇めて祀る目的で山麓に建てられた、
という説にも納得できるところがあります。
頂上付近に巨石のあるのがお分かりでしょうか。
「ふたり」に登場した不動岩です。
不動岩の先には浄土寺の奥の院があり、頂上には展望台も設けられています。
(山麓の浄土寺と山頂の奥の院は、艮神社と千光寺の関係にも重なります)
裏側からぐるりと回りこみ車で頂上近くまで行くことも可能ですが、
やはりそれでは味気ないですし自分の足で歩いて登りましょう。
それにしても遠いですねぇ・・・。
道を進むと「観音のこみち」というコースで頂上まで行くことができます。
ただくれぐれも気合を入れて。
標高差からも分かるように、かなり本格的な山道の「ハイキング」です。
当然、途中には水分補給できる飲み物の自販機も、水道もありません。
体力の消耗もかなりなものですから、
1日中歩き回ってへとへとになった夕方などには入山なさりませんよう。
街灯もなく昼なお暗い山道。
日が暮れると真っ暗ですし、急な斜面や断崖などもあってとても危険です!
(ここからの夕焼けは見事なのですが・・・)
お勧めは、午前中早く、まだ体力が十分ある時分ですね^^。
さあ、いよいよ入山です。
入口には細工の凝った石橋が架かっています。
瑠璃山への入山口なので「瑠璃橋」と名前がついています。
その昔、防地川の川下にあった芝居小屋・偕楽座の前にかかっていたもの。
大正時代に木橋から石橋に架け替えられたものが、
その後道路拡張のため解体され、同じく鉄道以南にかかっていた
他の橋の石材とともに浄土寺に預けられました。
昭和に入ってその材料を使って長さ約13mの石橋を完成させ、橋名を「瑠璃橋」と改めたそうです。
石工の町・尾道ならではの遺物といえますね。
続く
しげぞー
2009年07月02日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │おのみちまちあるき
「サマー・ウォーズ」上田市特別試写会
先日、このブログにて第一報をお知らせしたアニメ「時をかける少女」の
細田守監督の最新アニメ「サマー・ウォーズ」。
上田市が舞台となったこの夏の話題作です。
8/1(土)の全国公開に先駆けて、
7/20(海の日)に上田市にて特別試写会が実施されます。
細田守監督も来場されるということで、話題ですね。
しかし、上田市にお住まいの方限定の試写会ということで
ひがしざわは残念ながら涙を飲みます。
現在この試写会の申し込みを往復ハガキにて受付中です。
締め切りが7/6日必着なのでお急ぎ下さいね。
詳しくは
上田市役所サマーウォーズ特別試写会開催! ←こちらをクリック下さい☆

細田守監督の最新アニメ「サマー・ウォーズ」。
上田市が舞台となったこの夏の話題作です。
8/1(土)の全国公開に先駆けて、
7/20(海の日)に上田市にて特別試写会が実施されます。
細田守監督も来場されるということで、話題ですね。
しかし、上田市にお住まいの方限定の試写会ということで
ひがしざわは残念ながら涙を飲みます。
現在この試写会の申し込みを往復ハガキにて受付中です。
締め切りが7/6日必着なのでお急ぎ下さいね。
詳しくは
上田市役所サマーウォーズ特別試写会開催! ←こちらをクリック下さい☆






